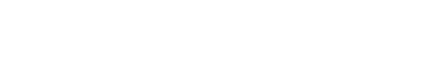安井氏のルーツ+
川田剛『安井息軒先生碑銘』は、安井息軒の祖先について次のように説明しています。
先生 諱は衡、字は仲平、号は息軒。先世は出羽の人、安東貞朝なる者有りて、上野介と為る。其の采安井村に徒りて、因りて氏を更む。七伝して家朝に到りて西して日向に徒り、飫肥侯の先 光台公に事ふ。家朝十四世の孫を朝中と曰ひ、朝中 朝長を生む。朝長の子、諱は朝完、字は子全、号は滄洲、学行を以て聞く。先生は其の次子なり。[川田剛『安井息軒先生碑銘』]
これによると、安井氏のルーツは出羽(山形県)にあったそうです。もともと安東氏を名乗っていましたが、①安東貞朝の代で上野介に叙せられ、所領となった上州(群馬県)の安井村に移り住んだのをきっかけに、名字を安東から安井に変えました。
①貞朝から数えて7代後の⑧家朝のときに日向(宮崎)へ移り、飫肥藩主の祖先である伊東祐持(光台公)に仕えました。この⑧家朝から数えて14代後の㉓朝中が息軒の曽祖父、その息子の㉔朝長が息軒の祖父、㉕朝完が息軒の父滄州で、息軒は26代目ということになります。
✦
安井氏のルーツについては、さらに詳しい資料が残っています。息軒が元治2年(慶応1/1865)に幕府に提出した身上書(『清武町史・資料編1』近世史料29)と安井氏に伝わる家系図(『清武町史・資料編1』近世史料30)です。
それによると、⑧家朝は延元1年(1336)に足利尊氏の「筑紫下向」に際して畠山直顕に従って関東から佐土原(宮崎市佐土原町)へ移った後、畠山直顕の口利きで伊東祐持の客分となります。それ以降、安井氏は伊東氏に仕え続けました。
日向伊東氏について:
工藤祐経という鎌倉武士がいました。源頼朝の配下でありながら、「曽我兄弟の敵討ち」(1193年)で暗殺された武将です。彼の息子祐時が「工藤」から「伊東」に改姓したのが、伊東氏の始まりです。そして祐時の息子の祐明が、父親から相続した日向国田島(宮崎市佐土原町田島)へ移住して、分家の田島伊東氏として一帯を支配し始めました。
建武2年(1335)、関東に残っていた本家の伊東祐持が、足利尊氏から日向国都於郡(宮崎県西都市)を拝領し、移住してきます。祐持は先住の田島伊東氏など分家を統合し、日向伊東氏を形成していきます。その翌年の延元1年(1336)に畠山直顕が室町幕府の南九州方面司令官のような立場で赴任してくると、伊東祐持はその配下に入ります。このとき畠山直顕に従って佐土原へやってきた⑧安井家朝を、客将として受け入れたのです。
天正5年(1577)、伊東氏は島津家久によって佐土原を終われ、流浪の身となります。その後、豊臣秀吉の九州征伐の先導役として宮崎に戻ってきます。その功績で秀吉より飫肥を拝領し、日向伊東氏は奇跡の復活を遂げました。「関ヶ原の戦い」では西軍として参戦しましたが、途中で東軍に寝返ったことで、徳川家康からも飫肥領支配を承認されました。
その後は、廃藩置県(1871)まで260年以上にわたって、伊東氏が飫肥を統治します。
天正5年(1577)、伊東氏が島津家久により佐土原を追われた頃は、安井氏は⑰朝重から⑱朝秀の代でした。⑰朝重と⑱朝秀はそのまま所領の平松郷に留まりました。やがて伊東氏が豊臣秀吉の先兵として日向に帰還すると、21歳になっていた⑱朝秀は旧主のもとに馳せ参じました。⑱朝秀は、その後も伊東の家臣として朝鮮出兵や宮崎城攻略に参戦し、多くの武勲を挙げたようです。
寛永2年(1625)、⑲朝堯が清武奉行として清武郷に赴任しました。これ以降、安井氏は㉕朝完(滄州)が藩校「振徳堂」総長に赴任するために飫肥城下へ引っ越すまで200年以上を、清武郷で暮らすことになります。
父 安井滄洲(そうしゅう)について+
安井滄洲(1767-1835)は生来の勤勉家で学問を好み、まず伯父の日髙源助より学問の手ほどきを受け、後には江戸で古谷昔陽(1734-1806)に、京都で皆川淇園(1835-1807)に学びました。清武に戻ってからは自宅(国の史跡「安井息軒旧宅」)で学問を教えるかたわら、赤江の「城ヶ崎俳壇」の一員として創作活動にもいそしみました。
安井滄州の文芸作品について:
当館常設展示室では、滄洲の紀行文『昼寝の友』『米良の見塩』『尚白集』『二日酔』『豊の秋』『梅が香』『卯の花』『ひとり旅』『温泉記』『梅見囃』および詩集の写本を展示しております。
内容をご覧に成りたい方は、当館では滄州の紀行文と随筆を翻刻した『安井滄州紀行集・滄州随筆』を販売しておりますので、お問い合わせ下さい。閲覧室には、くずし字で書かれた詩集を隷定した資料がご覧になれます。また鹿児島県立短期大学地域研究所の『研究年報』5にも『安井滄洲紀行集・ 付『志濃武草』 が収録されています。
文政10年(1827)、清武郷の人々の勧進によって郷校「明教堂」が創建されると、滄州は初代学長兼教授となり、息軒と父子で清武郷の教育に取り組み、平部嶠南や阿万豊蔵など後に飫肥藩の支柱となる人材を育て上げます。教師としての滄州・息軒父子について、門生だった和田重遠が「滄州先生、人を教ゆるに厳ならず。門人これを敬すること厳父のごとし。清瀧(息軒)先生は厳確なれども、門人これを親(したし)うこと慈母のごとし」(若山甲藏『安井息軒先生』)と伝えています。
もともと宮崎南部は尚武の気風が強く、「飫肥は西南の海隅に僻在し、士は樸陋に習ひて文事を喜ばず」(川田剛『安井息軒先生碑銘』)という土地柄だったのですが、現在の清武町は宮崎県随一の文教エリアとして知られています。その転換点は、安井滄州にあると言えましょう。
天保元年(1830)に藩校「振徳堂」設立の藩命が下ると、滄州は「振徳堂」初代総裁に任命され、息子夫婦(息軒と佐代)とともに清武郷中野から飫肥城下へ引っ越します。現在では清武から飫肥までは東九州道を通れば1時間とかからない距離ですが、当時にあっては容易に往来できる距離ではありません。実際、滄州は5年後に亡くなったこともあり、清武に戻ることはありませんでした。
さて、滄州は振徳堂でどういったことを教えていたのでしょうか。『滄州随筆』を見ますと、
友人問いて曰く、「朱子と徂徠との学風、何れかよろしきや」。予 答えて曰く、「一句一章の解き方には、何れも是もあり非もあるべし。然れども朱子の学は「性理」に泥して禅学に似たり。徠翁の学は礼楽を解し、其の外の事 多く古にかなうと云うべきか。然れども朱子学の弊を除かんため、言 激切に過ぎたる所あるべけれども、其の功も亦た大なり。近年人々学流を立つるものも、皆 徠翁の先登に従ふてなり。且つ徠翁を陽に非ずとするものも、陰に其の説を奪うもの多し。是れ徠翁の学力 大いに人に過ぎたる所あるなり。[安井滄州『滄州随筆』]
とあり、朱子学に否定的で徂徠学を高く評価していることが分かります。息軒は「寛政異学の禁」が施行されているにも関わらず、「古学」(山鹿素行・伊藤仁斎・荻生徂徠)を奉じて朱子学に批判的な立場をとっていたことで知られますが、それは息軒独自の境地というよりも、父滄州から継承した学問スタイルだったと言えます。息軒本人も『答某生論濮議書』のなかで次のように述べています。
年十五六、先君子に従い「四書」を講求するや、便ち已に疑ひ洛閩に有り。因りて条を挙げて之を質ただす。先君子曰く、「聖人の道は大にして,七十子の賢と雖も、僅かに其の偏を得るのみ。固より一家の説の能く尽す所に非ざるなり。乃ち徧く漢唐諸家及び我が伊・物諸先生の書を取りて之を読めば、恍然として得る所有るがごとし」と。[安井息軒『答某生論濮議書』]
ここで息軒は、自分が徂徠学を学び始めたきっかけは父滄州の助言だったことを明かしています。実際、慶応大学斯道文庫が保管する滄州の蔵書の中には『徂徠集三十巻補遺一卷』がありますので、少年息軒は清武の地でこれを読んだものと思われます。
飫肥城下へ移ってまもなく滄州は疝痛(腹痛)を患い、5年後の天保6年(1835)に亡くなります。その前年のことですが、息軒は公共事業をめぐって藩の上層部を批判して目をつけられていたこともあり、滄州は息軒に剛直さを慎むように遺言して息を引き取りました。息軒は滄州のために飫肥に墓碑銘を建てましたが、そこにこう記しています。
将に沒せんとするや、不肖衡を召して曰く、「我が年 幾ど七帙たり。汝も亦た粗ぼ能く家学を承け、死せんとするに恨む所無し。但だ汝の性 剛直なり。叔世の道に処るに非ずんば、謹んで之を戒めよ」と。不肖衡 正に垂泣して俯き聴く。俄かに旁人の哭するを聞く。驚き起こせば、則ち既に䏃せり。嗚呼、生くるや其の養を尽くす能はず、沒するや其の敎を奉ずる能はず。喪服纔く除くや、果して憎みを郷人に取り、遠く墳墓を去りて以て此の都に来たれり。[安井息軒『太平山表』(『息軒遺稿』収録)]
三年が過ぎ、父の服喪が明けたところで息軒は藩職を辞し、妻子を連れて江戸へ移ります。
参考:黒江一郎「安井滄州について」
妻 川添佐代+
森鷗外が『安井夫人』で描いた近代女性「お佐代さん」のモチーフとして有名です。鷗外は、宮崎のジャーナリストで郷土史家の若山甲蔵が大正2年に出版した『安井息軒先生』にインスピレーションを得て、『安井夫人』を書き上げたと言われています。
さて、川添佐代が息軒に嫁いだ経緯について、若山甲蔵『安井息軒先生』は次のように伝えています。
是れに就いて、極めて面白い逸話を誌そう。先生の郷里、清武村の大字今泉小字岡の川添氏(現時の主人を満と呼ぶ)は、滄州夫人の実家だが、姉妹の娘があって、姉は十人並み以下の嫖緻、名はお豊さん、妹は界隈には勿論、飫肥の城下にも較べる程のものが無いと云われた美人、名はお佐代さんで『岡の小町』と云われた人であった。
滄州翁は、其の姉の方を先生の嫁にくれとの相談をしたが、お豊さん曰く「いくら私が不器量だって、仲平さんのような、あんな不男は厭でござりまする」と、ツンとすねる。成る程申し条至極だというので、此の縁談は破れる所であったが、妹のお佐代さんが、内々母親への願いとあって「仲平さんのお嫁にやって下さい」と顔赧めての申し出、いづれも驚いたが、滄州翁も「美しい方なら此の上なしだ」と大歓び、「善は急げだ、日和の変わらぬ内に」というので、結納も済み、程なく「高砂や」と謡い納めて、イトコ同志の好き合った新夫婦が出来たのである。
而して彼の地、中野の弓削則徳氏の母堂は、姉のお豊さんの曾孫に当たるので、事実を詳しく知る人が多い。[若山甲蔵『安井息軒先生』]
この逸話に森鴎外はインスピレーションを得て、瞬く間に『安井夫人』(大正3年)を書き上げたわけですが、この嫁取りのシーンは特に力を入れて描写しています。その全てはとても引用できませんから、最後の部分だけ紹介しましょう。
お佐代はおそるおそる障子をあけてはいった。
母親は言った。「あの、さっきお前の言ったことだがね、仲平さんがお前のようなものでももらって下さることになったら、お前きっと往くのだね」
お佐代さんは耳まで赤くして、「はい」と言って、下げていた頭を一層低く下げた。
長倉のご新造が意外だと思ったように、滄洲翁も意外だと思った。しかし一番意外だと思ったのは壻殿の仲平であった。それは皆怪訝するとともに喜んだ人たちであるが、近所の若い男たちは怪訝するとともに嫉んだ。そして口々に「岡の小町が猿のところへ往く」と噂した。そのうち噂は清武一郷に伝播して、誰一人怪訝せぬものはなかった。これは喜びや嫉みの交じらぬただの怪訝であった。【森鴎外『安井夫人』】
日本で恋愛結婚が主流となったのは、1970年代のことだと言われています。それまでは親が決めた男性のもとに黙って嫁ぐのが当たり前の世の中でした。ましてや江戸時代です。そんな時代にあって、自ら夫を決めたという川添佐代のエピソードは相当にインパクトがあったのでしょう。あの芥川龍之介も好きな女性のタイプを聞かれて、
森先生の『安井夫人』と云う歴史小説の女主人公のような、際物じみない女が好いんですね。殊にそう云う人で、しっとり心に沾いのある、優しい気立ての人だったら、何、五世か六世位の美人でも有難く御説を拝聴します。
今云ったたような内外の美が具っている人があったらそりゃ僕もきっと惚れるでしょう。【芥川龍之介『僕の好きな女』】
と、川添佐代のような女性がタイプだと答えています。
✦
息軒の弟子で飫肥藩最後の家老となった平部嶠南は、『日向纂記』に次のような逸話を記しています。森鷗外『安井夫人』にも、少し改変されて収録されています。読み比べるとよいでしょう。
飫肥外浦の漁人に黒木孫右衛門と云う者あり。言語容貌、愚なるが如くなれども、頗る滑稽にして、能く人の意を邀へ、意表に出る話も多かりき。且つ物産の事に精しきを以て、天保の中頃、権要の人に用いられ、徒士席を賜うに至れり。
其の初めて安井息軒翁に見えし時、従容として申しけるは、「先生の内君は学問し玉えるか」。翁 何心なく「未だ学びたることなし」と答えらる。孫右衛門 申しけるは、「今先生の御容貌を窺い見るに、長さ五尺に過ぎず、殊に痘痕面に満ちて甚だ醜し。然るに内君少しも厭う心なく、先生の徳を慕うて、身を託し玉えるは、中々尋常婦人の能く及ぶ所に候はず。其れ故、某は先生の学よりは内君の学が勝れりと思うなり」と。翁も手を拍って大いに笑われける。【平部嶠南『日向纂記』】
このころ黒木孫右衛門というものが仲平に逢いに来た。もと飫肥外浦の漁師であったが、物産学にくわしいため、わざわざ召し出されて徒士になった男である。お佐代さんが茶を酌んで出しておいて、勝手へ下がったのを見て狡獪なような、滑稽なような顔をして、孫右衛門が仲平に尋ねた。
「先生。只今のはご新造さまでござりますか」
「さよう。妻で」恬然として仲平は答えた。
「はあ。ご新造さまは学問をなさりましたか」
「いいや。学問というほどのことはしておりませぬ」
「してみますと、ご新造さまの方が先生の学問以上のご見識でござりますな」
「なぜ」
「でもあれほどの美人でおいでになって、先生の夫人におなりなされたところを見ますと」
仲平は覚えず失笑した。そして孫右衛門の無遠慮なような世辞を面白がって、得意の笊棋の相手をさせて帰した。【森鷗外『安井夫人』】
その一方で、若山甲蔵『安井息軒先生』に記されていて、森鷗外が採用しなかった逸話もあります。長女須磨子の話なのですが、森鷗外は
仲平夫婦は当時女中一人も使っていない。お佐代さんが飯炊きをして、須磨子が買物に出る。須磨子の日向訛りが商人に通ぜぬので、用が弁ぜずにすごすご帰ることが多い。【森鷗外『安井夫人』】
とさらっと流していますが、森鷗外が参考にした若山甲蔵『安井息軒先生』は次のような興味深い逸話を伝えています。
先生は、質素に暮らされたが、夫人は一人心こまかに経済を図った。先生が江戸へ移った際は、学僕もいず、下女も使わないで、十一歳に成る長女寿満子を相手に、住みも慣れぬ都の真ン中で、何かと苦労をせられたもので、買い物等は、不案内な寿満子が出るので、「田舎者」と嘲り笑われたのも幾度か知れぬ。「詞の通じないのが何より辛かった」とは、寿満子が後日譚にあったそうな。其の頃、お客でもあれば、夫人が手料理の二種三種、夜分は蕎麦二椀を下物に出すことに極めていた。然し、「父上 ご出世は疑いなし」との夫人が言葉に、寿満子も勇気が出る心地したとの事、是れも寿満子が懐かしき思い出の一つ。【若山甲蔵『安井息軒先生』】
この”母佐代の「父上 ご出世は疑いなし」という言葉に、東京(江戸)に出てきたばかりで方言を馬鹿にされて悔しい思いをしていた娘須磨子は非常に勇気づけられた”という印象深い逸話を、森鷗外はバッサリ削っています。この逸話があるのとないのでは、読者が抱く川添佐代の印象はずいぶんと違ってくるように思います。
しかし、この逸話が隠されていることによって、最後の「お佐代さんは何を望んだか。世間の賢い人は夫の栄達を望んだのだと言ってしまうだろう。これを書くわたくしもそれを否定することは出来ない。しかし……その望みの対象をば、あるいは何物ともしかと弁識していなかったのではあるまいか」(森鷗外『安井夫人』)という一文が印象深いものに仕上がっていることも、また確かです。
いずれにせよ、『安井夫人』は歴史小説(歴史離れ)であって、伝記(歴史そのまま)ではないことに、充分注意を払う必要があります。