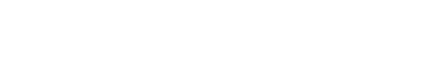常設展示室・展示品(その1)
川田剛『安井息軒先生碑銘』
書き下し文
清國 誥授・資政大夫・布政使銜・前江蘇按察使・應寶時 篆額
- 文久中、大將軍德川公の師儒を妙選するや、其れ擢かれて藩國より昌平黌敎官に列せられし者三人、曰く山形の鹽谷毅侯、曰く田中の芳野叔果、而して其の一は則ち飫肥の安井先生なり。先生は齒 最も長く、學 最も邃く 、議論文章最も醇にして且つ正たり。然れども是の時四方故多く、幕府の政衰へり。先生屢々獻言するも、當路 報いず。晩に白河代官に任ぜらるるも亦た未だ行かずして罷め、乃ち老を告げて致仕す。專ら著述を事とし、學ぶ者其の書を傳誦す。安井先生の名は、遠く海外に聞こゆ。
- 先生は長さ六尺に満たず、貌寢なるも識は明たり、色は溫なるも氣は剛たり。飫肥は西南の海隅に僻在し、士は樸陋に習ひて文事を喜ばず。先生獨り發憤して讀書し、矻矻として匪懈して、曰く「吾 六經を治むるは、物を開き務を成さんと欲すればなり。不幸にして吾が道行はれずんば、則ち之を文字に託して、當に知己を天下後世に求むるべし。夫の區區たる毀誉のごときは、以て齒牙に置くに足りず。」と。
年甫 冠を踰え 、東して大阪に游び、篠崎小竹に見ゆ 。小竹 與に語りて大いに驚き、詩を賦して之に贈る。後に江戸に至りて、昌平黌に入り、松崎慊堂の門に執贄す。慊堂は一世の宿儒にして、人に許可するを愼む。其の徒に語りて曰く、「安井生は、古人なり。吾 豈に弟子もて之を畜ふべけんや」と。其れ《石經》を考訂するに、多く之を先生に詢ると云ふ。 - 文政丙戌、飫肥侯 東覲し、舉げて侍讀と爲す。明年藩學を創建して助敎に遷し 、命じて九州を巡覽せしむ。乃ち《觀風抄》一巻を撰して之を上す。侯 其の用ふべきを知りて、引きて謀議に參ぜしむ。權要の格む所と爲り、 先生 悅ばず。
- 天保乙未、丁父憂す。服闋して、辭職す。東行して、再び昌平黌に入り、寓を增上寺僧寮に尋ね、戸に楗して苦學す。以て聖賢の出處進退の旨を究め、禮樂兵刑の古今沿革の故を考ず。畜ひては道德を爲し、發しては言論を爲す。恍乎として得ること有るがごとく、恢恢乎として餘地有り。其れ徒を聚めて業を授くるに及べば、四方の俊秀來りて門下に集ひ、曩時 先生を忌む者も先後す。即ち世輿 誦翕す。然らば侯 乃ち擢きて參政と爲し、祿百石を給す。先生 病を移して間を請ふも、仍ほ機務を預聞す。
- 嘉永癸丑 、米利堅 互市を求む。諸侯 各々邊備を修む。先生謂らく「羊質にして乕皮を蒙れば、其れ敗を取らざる者幾ど希し」と。因りて《海防私議》一巻を著し、製艦・鑄礮・築堡・畜穀の方を論ず。水戸烈公 聞きて之を善みし、其の臣藤田彪をして就ち時務を詢らしめ、且つ手ら「食を足らし、兵を足らし、民をして之を信ぜしむ」の八字を書して以て贈る。他日左右と兵を談ずるに、輙ち曰く「乃ち羊質にして乕皮すること無からんか」と。是に於いて先生の聲望日に隆まり、幕府も之を辟して、給ふに祿米二百苞・職俸十五口糧を以てす。舊制にては林氏 世々學政を掌り、經を說くに專ら朱注を用ふ。先生は古學を崇尚すれば、顧みるに此の選に膺るは、異數なり。
- 慶應丁卯 詔して幕府を廢す。明年、六師 東して下る。府兵 往往にして屯聚して命を拒む。先生 門弟子の或ひは之に黨するを慮りて、地を郊外に避く。彥根侯 業を先生に受けて、館の別業に請ひ、二十口糧を餽りて、禮待 備至たり。然れども先生 舊君を思ひて已まず、飫肥に復籍せんと欲す。飫肥侯 延きて世子の師と爲し、三十口糧を餽る。固辭するも許さず、遂ひに其の半を受く。或ひは之を朝に推薦する者有るも、老耄を以て辭す。某親王 召して經を講ぜしめんとするも、亦た辭して往かず。曰く「西方の鄙人、禮節に嫺はず」と。
- 初め先生 鹽谷・芳野・羽倉・木下・藤森諸儒と文社を結す。剛 後進を以て濫りに其の間に厠る。是に至りて耆宿 凋謝して、其れ魏然として存する者は、獨り先生と芳野子と有るのみ。而して先生 則ち衰へ且つ病めり。一日病間に剛を招きて臥内に入らしめ、手を執りて舊を話し、囑むに墓銘を以てす。剛 唯唯流涕して退く。三日を越えて、逐に起きず。悲しいかな。
- 先生 諱は衡、字は仲平、號は息軒。先世は出羽の人、安東貞朝なる者有りて、上野介と爲る。其の采安井村に徒りて、因りて氏を更む。七傳して家朝に到りて西して日向に徒り、飫肥侯の先 光臺公に事ふ。家朝十四世の孫を朝中と曰ひ、朝中 朝長を生む。朝長の子、諱は朝完、字は子全、號は滄洲、學行を以て聞く。先生は其の次子なり。寛政巳未正月朔旦、日向清武郷中野里に生まれ、明治丙子九月二十三日、東京土手三番街僑居に終はり、駒籠の養源寺の塋に葬る。享年七十有八。
- 川添氏を娶り、二男を生み、朝隆と曰ひ、謙助と曰ふ。並びに先歿すれば、謙助の遺孤千菊を以て後を承けしむ。四女ありて、一は島原の人北有馬太郎に適くも、餘は皆な早く亡す。
- 先生は篤く信じて古を好み、尤も力を漢唐の注疏に用ひ、參ずるに衆說を以てし、能く先儒の未だ發せざる所を發す。文を爲るに法を唐宋に取り、上は秦漢に溯り、古色蒼然たり。旁ら算數に暁く、嘗て曰く「聖門の六藝、數は其の一に居りて、經國行軍、由らざる莫し。近世の學者は、性命を高談して、曾て二五の十たるを解かず」と。流に沿ひて源を討てば、宋儒も其の責を辭するを得ず。
- 門人に洋敎の是非を問ふ者有るや、爲に《辨妄》一卷を撰す。然れども天文・地理・工技・算數に至っては、則ち洋說を参取す。以て其の持論の公なるを見るべし。
- 性は淡泊にして、儉素をば自ら奉じ、特だ圍棊を嗜むのみ。其れ白河を宰するの命 始めて下るや、吏胥 來たりて賀するに、燦然たる華服して、各々酒饌を齎す。先生 垢衣敝氈して、延きて與に對局し、供するに踈糲を以てするに至りて、乃ち愧赧して去る。更に相ひ告誡すれば、未だ赴任せずして邑俗は奢靡を革むと云ふ。
- 著す所の《管子纂詁》十二巻・《左傳輯釋》二十一巻・《論語集說》六巻・《息軒文鈔》四巻、世に梓行せらる。《書說摘要》四巻・《孟子定本》六巻・《戰國策補正》二巻・《読書餘適》二巻・《靖海問答》一巻・《料夷問答》一巻・《外冦問答》一巻・《軍政或問》一巻・《忍草》一巻・《睡餘漫筆》三巻、其の他三禮・《毛詩》諸書の注釋の未だ脱稿せざる者、又た若干巻、 並びに家に藏す。
- 先に是れ清國江蘇按察使の應寶時は《管子纂詁》・《左傳輯釋》を讀みて、其の精核なるを稱へて爲に序文を製る。朝鮮禮曹參議の金綺秀は來聘するに、人に告げて曰く「吾 聞くならく『日本に安井先生有り』と。恨むらくは歸期 已に迫れば、相ひ見ゆるを得ざるを」と。乃ち「息軒」の二字を書して之に贈る。鳴呼、先生 外人の推服する所と爲ること此くのごとければ、則ち海內の欽仰 は知るべし。
- 銘に曰く
世 新奇を尚ぶも 我 獨り古を愛す
世 浮華に趨るも 我 獨り素を守る、と
卓なるかな先生 儒行に愧じず
禮を講じ經を治むるに 馬・鄭を追踪す
先生 在せば 師は嚴にして道は尊ばる
先生 亡すれば 孰か斯文を興さん
明治十一年九月 修史館一等編修官・從五位・川田剛撰 太政官大書記官・從五位・日下部東作書 廣羣鶴刻字
口語訳
清国の誥授・資政大夫・布政使銜・前江蘇按察使の應寶時が篆額を書いた。
- 文久二年[一八六二]、徳川幕府は教師にふさわしい儒学者を全国から選んだ。諸藩から抜擢されて、三名の学者が昌平黌[※昌平坂学問所]の教授に列せられた。一人は山形藩[静岡県掛川市?]の塩谷毅侯[塩谷宕陰:一八〇九~一八六七]、一人は田中藩[静岡県藤枝市]の芳野叔果[芳野金陵:一八〇三~一八七八]、そして最後の一人が飫肥藩[宮崎県日南市飫肥]の安井先生である。先生は三人のなかで最年長者であり、その学問は最も奥深く、議論と文章は最も純正だった。しかし、この頃の日本は内外ともに多事多難で、幕府の政治は衰えていた。先生はたびたび幕府に意見を上申したが、用いられなかった。晩年には白河[現在の福島県白河市]の代官に任命されたが、一度も赴任することなく辞任し、そのまま高齢を理由に退職した。それからは著述に専念し、学問を志す人々は先生の著作を読み伝えた。先生の名声は遠く海外にまで知れ渡った。
- 先生は背丈が六尺[一四四センチ。中国の尺度で一尺は二四センチ]足らずで、小柄で容貌は醜かったが学識は素晴らしく、外見は温和だったが内面は剛毅であった。飫肥藩は西南の海に面した僻地にあり、藩士は朴訥で見識が浅く、文化的なことを好まなかった。そんな中、先生はひとり発奮して書物を読み、コツコツと勉学して怠ることがなかった。当時から先生は「自分が儒教の経典[※六経]を学ぶのは、〔『周易・繋辞傳』にあるように〕人々を啓蒙して、世の中のためとなる事業を成し遂げたいからだ。〔けっして自己満足のためではない。〕もし不幸にして私の主張や考えが世間で受け入れられなければ、それを文字に託して、遠い後世に理解者を求めよう。取るに足りない毀誉褒貶など、一々歯牙にかけるに値しない」と言っていた。
- 年の初め、年齢が二〇歳を超えると、先生は東行して大阪に遊学し、篠崎小竹[一七八一~一八五一]に会った。小竹は先生と語ってその学才に驚き、漢詩を作って先生に贈った。その後、先生は江戸に出て昌平黌に入学し、松崎慊堂[一七七一~一八四四]に家塾に入門した。慊堂は当時を代表する高名な儒学者で、他人を軽々しく評価することはしなかった。だが、門弟たちに「安井君は若くしてすでにいにしえの学者の風格がある。どうして弟子扱いできようか」と言い、『唐石経』の校勘に際して先生に意見を求めることが多かったという。
- 文政九年[一八二六]、飫肥藩主伊東祐相[一八一二~一八七四]は参勤交代で江戸に来ると、先生を侍読[※君主の側に仕えて学問を教える学者]に任命した。明くる年[※実際は五年後]、飫肥藩校「振徳堂」を創建し、先生を飫肥に戻して助教とし、さらに九州全域の視察を命じた。先生は『観風抄』一巻を著述し、これを献上した。飫肥藩主祐相侯は先生を重用すべきだと分かったので、抜擢して重要な政務に参画させた。〔しかし家老たち〕権力の要職にある者たちに邪魔をされて、先生は不満であった。
- 天保六年[一八三五]、父親の滄州が亡くなった。喪が明けると、先生は藩職を辞して江戸へ出て、再び昌平黌へ入学し、増上寺の僧寮に寄宿した。部屋に閉じこもって苦学し、いにしえの聖人や賢者の出処進退に対する考え方を研究し、礼制・音楽・軍事・刑罰の古今の沿革の原因について考究した。学んで得たことは、内には道徳として蓄え、外には言論として発表した。その頃の先生はうっとりとした表情で何かを悟りを得たようであり、ゆったりとして余裕があった。先生が〔三計塾を開いて〕門徒を集めて授業をするようになると、全国各地から優秀な人材が門下に集(つど)った。しかも、かつて先生を嫌った〔飫肥藩の〕者まで列をなした。世間の衆望が先生に集まった。それゆえ飫肥藩主祐相侯は先生を家老に次ぐ用人格に抜擢し、百石の俸祿を与えた。先生は病気を理由に辞職したが、引き続き藩政の機密に係わり続けた。
- 嘉永六年[一八五三]、米国が通商を求めてきた。諸藩はそれぞれ国境〔となる海岸〕沿いの防備を固めた。先生は諸藩の対応を見て「トラの皮をかぶったヒツジ[※外見だけで中身が伴わない]だ。外国の軍隊に敗北しない藩はほとんどないだろう」と思って、『海防私議』一巻を著して、軍艦を建造し、大砲を鋳造し、堡塁を築き、糧食を備蓄する方法について論じた。水戸藩[茨城県水戸市]の徳川斉昭公[徳川斉昭:一八〇〇~一八六〇]はこれを聞いて称賛し、家臣の藤田東湖[一八〇六~一八五五]に命じて時事問題について先生に相談させ、さらに自ら『論語・顔淵』で孔子が子貢に言った「足食足兵民信之矣」(政治とは、食料を充足させ、軍備を充足させ、人民に信義を守らせることだ)という八文字を掛け軸に書いて先生に贈った。他日、斉昭公は周りの者と軍事について談義する時に、よく「それは『トラの皮をかぶったヒツジ』ではないか」と言うようになった。〔先生の影響である。〕このようにして先生の声望はますます高まっていった。〔それで冒頭に述べたように、ついに〕幕府は先生を召し抱えて、祿米二〇〇俵と職給一五糧を与えた。旧来の制度では、〔徳川家康に仕えた朱子学者である林羅山に始まる〕林家が大学頭を世襲して学政を掌握しており、〔昌平黌でも〕専ら朱子学で経書を解説していた。先生は〔朱子学を批判する荻生徂徠・伊藤仁斎・山鹿素行に始まる〕「古学」を信奉していたので、この抜擢は全く異例のことであった。
- 慶應三年[一八六七]、〔徳川慶喜の「大政奉還」を受け入れるという〕勅命によって幕府が廃止された。翌年には官軍[※天子が率いる軍団を「六軍」と呼ぶ]が東征して江戸に入った。官軍の兵士たちはしばしば集まって〔は狼藉を働き、〕軍規に背いた。[※江戸城下の旧幕府軍の兵士たちはしばしば集まって〔は気炎を挙げ、降伏せよという〕朝命を拒否した。]先生は〔自分とともに江戸に留まっている〕門弟たちが勤王と佐幕の党派に分かれて争いだすことを心配して、江戸の郊外に難を避けた。彦根藩の井伊直憲侯[一八四八~一九〇四]は先生に学業を受けていたが、先生に彦根藩の江戸別邸に移るよう請い、その上で二〇口糧を贈り、礼を尽くして迎え入れた。しかし先生は旧君を慕う思いが消えず、飫肥藩への復籍を願い出た。[※息軒は昌平黌の教授となった時点で、飫肥藩籍を抜けて徳川直参となっていた。]飫肥藩主祐相侯は先生を招いて世子[※世継ぎ]の師とし、三〇口糧を贈った。先生は固辞したが、祐相侯は許さず、先生はやむなく半分の一五口糧を受け取ることにした。また、先生を朝廷に推挙する者もいたが、先生は高齢を理由に辞退した。ある皇族も先生を経書を教える侍読として招請しようとしたが、先生は「西方の田舎者は、礼儀作法に不慣れなので」と言って辞退して、行かなかった。
- 初めに先生と塩谷宕陰・芳野金陵・羽倉簡堂[一七九〇~一八六二]・藤村弘庵[一七九九~一八六二]らの儒学者たちが「文会」を結成した。私こと川田剛[川田甕江:一八三〇~一八九六]は後進の若輩ながら分不相応にもそのなかに交わらせていただいた。今ここに至って学徳に優れた老大家たちは次々と亡くなり、泰然自若として存命なのは、ただ先生と芳野先生のみである。そして先生も身体が衰え、病気がちになった。病状が持ち直したある日、先生は私川田剛を病床に招いて、私の手を握って昔の思い出を語り、自分の墓碑銘を書くことを私に依頼した。私は[先生から文才を認められたことに感動して]涙を流しながら「はい」と答え、退室した。その三日後、先生はついに逝去した。本当に悲しいことである。
- 先生は諱(名)は衡、字を仲平、号を息軒といった。先祖は出羽(山形県)の人で安藤貞朝という。上総介となって、領地である安井村に移り住み、村名にちなんで氏を「安井」と改めた。貞朝から数えて七代目の家朝の時に、西行して日向(宮崎県)に移住し、飫肥藩主の祖先である光台公に仕えた。家朝から十四代目の子孫を朝中といい、朝中には朝長という子が生まれた。朝長の子は諱(名)を朝完、字を子全、号を滄州といい、学識と徳行が高く評判となった。先生はその次男である。先生は寛政一一年[一七九九]一月一日に日向国清武郷中野[宮崎市清武町中野]で生まれ、明治九年(一八七六)九月二三日に東京土手三番町の自宅で逝去し、駒込の養源寺の墓地に葬られた。享年七八歳であった。川添氏の娘と結婚し、朝隆と謙助という二人の息子が生まれたが、二人とも早く死んだので、謙助の遺児千菊が跡を継いだ。四人の娘がいて、一人は島原[長崎県島原市]出身の維新志士北有馬太郎[一八二八~一八六二]に嫁いだ。他はみな早く世を去った。
- 先生は古い時代の学問を好み、その正しさを厚く信じていた。漢代に作られた「注」と唐代に作られた「疏」の解釈に最も力を注いだが、他の多くの説も参考にし、過去の儒学者が誰もまだ言っていない新説を発表した。漢文の文章は唐代と宋代の文体を取り入れ、古くは秦代や漢代の文体にまで遡って参考にし、まさに古色蒼然の趣きがあった。その一方で算術にも精通し、かつて「孔子が門下生に教えていた「六芸」だが、数学はそのうちの一つであって、国家の経営や軍隊の運用で、数学を使わないということはない。それなのに近年の儒学者は〔「人間の本質とは何か」という〕「性命論」について高尚そうなな談義をするばかりで、〔実務となると〕二✕五は一〇という問題すら解けない」と言った。〔先生は議論する時は常に相手の論理の〕流れに沿って、その本源を突くので、朱子学者(宋学)もその詰責を逃れることはできなかった。
- 門人にキリスト教の是非を問う者がいたため、『弁妄』一巻を著述した。〔この書は、キリスト教を排撃したことで知られる。〕しかし、天文・地理・工業技術・算術は西洋の学説を取り入れ、参考とした。これを見ても先生の持論が公平であることが判る。
- 先生の性格はさっぱりとしていて、質素倹約を信条とし、趣味といえば囲碁だけだった。白河の代官に任命された時、任地の役人たちが祝賀にやってきたが、みな華美な服装をしてそれぞれ祝いの酒と肴を持参してきた。先生が垢だらけの衣服にボロボロの上着をまとって彼らを家に招き入れ、碁の対局をし、玄米でもてなすに至って、彼らは〔自分たちの虚栄心に恥じ入り〕赤面して帰っていった。〔白河に戻ってからも〕更に互いに戒めあったので、まだ先生が赴任していないのに、任地の習俗は改まり、贅沢をしなくなったという。
- 著書の『管子纂詁』十二巻・『左傳輯釈』二十一巻・『論語集説』六巻・『息軒文鈔』四巻は上梓され世に出た。また『書説摘要』四巻・『孟子定本』六巻・『戰国策補正』二巻・『読書余適』二巻・『靖海問答』一巻・『料夷問答』一巻・『外冦問答』一巻・『軍政或問』一巻・『忍草』一巻・『睡余漫筆』三巻や、その他『儀礼』『周礼』『礼記』の三礼や『毛詩』などの注釈書で未脱稿のものが若干安井家に所蔵されている。
- 以前、清国の江蘇按察使の応宝時は先生の『管子纂詁』と『左傳輯釈』を読み、先生が詳しく調べ、細かく考察していることに感心し、この二書のために序文を作った。朝鮮の礼曹参議の金綺秀は、来日した時、人に「日本には安井先生という学者がいると聞いていたが、帰国の時期が迫り、会えなくて残念だ」と語り、「息軒」の二文字を揮毫して贈った。ああ、先生は外人にもこれほど心服されていたのだから、まして国内ではどれだけ尊敬され慕われていたか分かるだろう。
- 銘文に述べる。
-
-
- 〔先生はおっしゃった。〕「世間の人々は新奇なものをありがたがるが、私は一人古い伝統を愛する。
- 世間の人々は上辺の華やかさを追いかけるが、私は一人簡素さを守る」と。
- 卓絶していることだよ、先生は。「儒行」(儒者の守るべき行い)に照らし合わせても恥じるところがない
- 礼学を講義し経学を修めるにあたって、後漢の馬融と鄭玄の学説を追い求める
- 先生がいらっしゃればこそ、教師は尊厳であって、学問の道は尊重されていた。
- 先生が亡くなった今、誰が聖人の道を盛り立てることができるだろう、いや、誰にもできない。
-
明治十一年九月 修史館一等編修官・従五位・川田剛が撰述し、太政官大書記官・従五位・日下部東作が清書し、広群鶴が字を刻んだ。