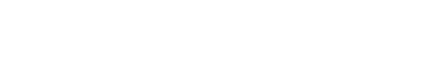息軒の師+
篠崎小竹+
篠崎小竹(1781-1851)は、息軒が20歳で大阪へ遊学した時の師です。江戸時代後期に大阪で活躍した朱子学者で、その私塾「梅花社」は当時大阪で最も盛んな塾でした。書家としても優れていました。
篠崎小竹は大阪で医者の次男として生まれ、9歳で徂徠学派の篠崎三島の私塾「梅花社」に入門し、徂徠学を学び始めます。13歳で篠崎三島の養子となりますが、やがて徂徠学に疑問を抱くようになり、18歳で江戸へ遊学した際には尾藤二洲(1745-1814)・古賀精里(1750-1817)に入門して朱子学を学びます。大阪へ戻ってからは家学の徂徠学に専念していましたが、28歳の時に無断で江戸へ行くと、再び古賀精里に入門します。間もなくして養父三島の許しを得て本格的に朱子学に転向し、文化5年(1808)に「梅花社」を継いで朱子学を教え始めます。息軒が入門するのは、その12年後、文政3年(1820)のことです。
篠崎小竹は当時21歳の息軒青年と語ってその学才に驚き、漢詩を作って送ったそうです(川田剛『安井息軒先生碑銘』)。ただ息軒の方ではそこまで篠崎小竹に感じる所はなかったらしく、後年弟子に語って「本国にありては書籍に乏しきゆえ上坂せし事なれば、別に師家を取る年もなかりしか、当時蔵書家と聞こえたる篠崎小竹は、その門に入らねば書物を貸さぬ由につき、同氏の門に贅を取り、書籍を借覧せり」(谷干城『隈山詒謀録』)と語っています。
ちなみに息軒は書家として名高かった篠崎小竹から書を教わろうとしたのですが、篠崎小竹に「江戸に一先生有りて、天下の拙書なり。然れども亦た能く一家を成す。子も亦た宜しく一家を成すべし。書 何を以てか学ぶことを為さん」と笑って断られたことで、自分には書の才能が無いと見切りをつけたのだとか(安井息軒『跋慊堂先生千文』)。息軒に揮毫が極端に少ないのは、そのせいかもしれません。
古賀侗庵+
古賀侗庵(1788-1847)は、息軒が25歳で江戸へ出て、昌平坂学問所に入寮した時の師です。息軒が38歳で昌平坂学問所に入り直した時には、古賀侗庵は息軒を昌平坂学問所の斉長(寮長)に指名しました。息軒は嫌がって一度は逃げましたが、侗庵の依頼を断りきれず、最後には引き受けています。
古賀侗庵は昌平坂学問所の儒官でしたが、朱子学のみならず諸子百家(道家・墨家・法家・陰陽家・縦横家・兵家など)にも通じていました。『海防臆測』をはじめ、非常に多くの著述を残しました。また父親の古賀精里(1750-1817)も昌平坂学問所の儒官だった人で、篠崎小竹に朱子学を教えました。
古賀侗庵は肥前(佐賀)で佐賀藩士古賀精里の三男として生まれました。父親から朱子学を学び、後には柴野栗山(1736-1807)から諸子百家を学びました。寛政8年(1796)、8歳の時に父親が昌平坂学問所の儒官に着任することなり、一緒に江戸へ移住しました。文化6年(1809)、21歳で「儒者見習」となって父親とともに昌平坂学問所で働き始めます。そして父親が文化14年(1817)に逝去すると、29歳で正式な儒官に昇進しました。儒官は世襲というわけではなく、古賀精里とともに「寛政の三博士」と呼ばれた柴野栗山や尾藤二洲の子供たちは儒官になっていません。
古賀侗庵は朱子学者でしたが、形而上学よりも実務を非常に重視するタイプの儒者でした。黒船が来航するずっと以前にロシアの脅威を訴え、国防力の増強すべきだと説き、大型外洋船の建造や西洋製の火器類の導入を提言していました。ロシアに関する分析の中では北海道のアイヌ民族やキリスト教の教義についても言及していますが、そこで示されたアイヌ観やキリスト教観は安井息軒の『蝦夷論』や『弁妄』に影響を及ぼしているように思われます。
弘化4年(1847)に没し、東京都文京区大塚の先儒墓地に埋葬されました。同墓地には儒官たちの墓が約60基あります。
松崎慊堂+
松崎慊堂(1771-1844)は安井息軒が27~28歳の頃に江戸で学んだ師です。息軒が江戸へ移住したばかりで収入が無くて困っていた時に、佐倉藩(千葉県佐倉市)藩儒に推薦したのは松崎慊堂です。『慊堂日記』には、息軒が何度も登場します。
松崎慊堂は掛川藩(静岡)の藩儒で、「日本漢唐学の鼻祖」と謳われる学者です。漢唐学というのは、儒学の経書を読む時に宋代に成立した朱子学や明代に成立した陽明学の解釈を退け、より古い漢代や唐代の注釈に準じて解釈しようとする立場です。中国で唐代に作られた石刻の経書『開成石経』を校訂して出版しました。
松崎慊堂は肥後(熊本)の農民の家に生まれました。10歳の時に地元の寺に預けられて勉学を始めますが、15歳の時に儒者になろうと決意し、江戸に出奔します。その後、浅草称念寺の僧の世話で昌平坂学問所長官の林錦峰の門人となるや、たちまち頭角を著し、佐藤一斎(1772-1859)と並び称されました。
慊堂はもともと朱子学を奉じていたのですが、友人で民儒の狩谷棭斎(1775-1835)が清朝考証学の手法を取り入れるのを見て、やがて考証学に転向しました。息軒の漢籍注釈のスタイルが考証学なのは、慊堂に準じたものと言えます。
ただし慊堂は息軒について初対面から「安井生は、古人なり。吾 豈に弟子もて之を畜ふべけんや」(川田剛『安井息軒先生碑銘』)とその学識を高く評価し、『開成石経』を校訂する際には息軒に色々と相談したそうです。
また慊堂の弟子には「蘭学にて大施主」(藤田東湖)と評された渡辺崋山(1793-1841)がいました。崋山が「蛮社の獄」(1840)で捕らえられた際、慊堂は水野忠邦に意見書を提出して、崋山を弁護しました。息軒は「大の西洋嫌い」(相馬永胤『懐旧記』)と言われる一方で、「天文・地理・工技・算數に至っては、則ち洋説を参取す」(川田剛『安井息軒先生碑銘』)という態度で知られますが、西洋の学問に対する公平さも、もしかしたら華山に対する慊堂の姿勢から学んだのかもしれません。
慊堂は天保15年(1844)に亡くなり、東京都目黒区長泉院の墓地に埋葬されました。
息軒の友人+
故旧 交際を結んだ順に述べる。
①塩谷甲蔵:山形藩教授。名は世弘、字は毅侯、号して宕陰。
②佐田修平:久留米藩儒官。号して竹水。名と字は忘れた。
③井上彦一:久留米陪臣(久留米藩主の家臣の家来)
④堀七太夫:会津藩。字は子遜。
⑤牧園進士:柳川儒官。
右の五人とは昌平坂学問所で交際を結んだが、毅侯(塩谷宕陰)が一番親しい。他の四人とも友情は密なのだが、住所が互いに遠すぎて、最後に会って数十年にもなる。ただ青年時代の旧交というのものは忘れられないので、巻頭に挙げておくことにした。
⑥木下真太郎:熊本藩儒官。名は業広、字は士勤、号して犀潭。
⑦岡長嘉右衛門:久留米儒官、後に致仕す。名は某、字は世襄、号して松陽・一号・蘭洲。
⑧川西確助:三州挙母藩儒官。号して函洲。
⑨古賀大一郎:佐賀藩儒官。
⑩芳野立蔵:田中藩儒官。名は育、字は叔果、号して金陵。
⑪藤森恭助:処士。名は大雅、号して弘庵。
⑫羽倉外記:幕士。名は用九、字〔は子乾、〕号しては簡堂。
⑬藤田誠之進:水戸。名は彪、号して東湖。
塩谷宕陰+
息軒にとって最初の友人です。息軒が初めて昌平坂学問所に入寮した時から付き合いで、知り合った当時、息軒は25歳で、宕陰はまだ15歳でした。宕陰の背が高かったので、背が低い息軒が並んで歩いていると、「宕陰は雲の上を歩き、息軒は草の下を歩いている」と言われたそうです。
息軒の後を追うように松崎慊堂に入門し、息軒が飫肥へ帰郷すると「明教堂記」を作って送りました。息軒が江戸へ移って来てからは、一緒に「文会」という文芸サロンを立ち上げて、毎月、顔を合わせて互いの文章を批正していました。(高橋智「塩谷宕陰・木下犀譚批評安井息軒初稿『読書余適』」)また息軒の長女須磨子と北有馬太郎の媒酌人を務めるなど、交際は公私に渡りました。
宕陰は師事した慊堂の推挙で浜松藩(静岡)の水野忠邦に仕え、水野忠邦が老中となって「天保の改革」を進めた際には顧問役として尽力しました。息軒や吉野金陵とともに昌平坂学問所の儒官に抜擢され、「文久の三博士」と呼ばれました。
芳野金陵+
吉野金陵(1803-1878)は、下総国(千葉・茨城)葛飾郡の儒医の次男として生まれました。幼い頃は父から漢文の読み方を学び、長じて下総関宿藩の儒官で折衷学派の亀田綾瀬に師事しました。
ちなみに亀田綾瀬の父親は亀田鵬斎といい、「寛政異学の禁」で「異学五鬼」の一人として幕府から弾圧された人物です。金陵は初めこの鵬斎に師事しようとしましたが、老齢を理由に断られ、跡継ぎの綾瀬に入門したそうです。金陵の学問的傾向がうかがえると同時に、彼がなぜ息軒と友人だったかがよく分かります。
金陵は23歳で江戸に私塾「逢原堂」を開きます。やがて息軒が江戸へ移り住んでくると、一緒に「文会」という文芸サロンを立ち上げます。44歳で駿河(静岡)田中藩の儒官となり、文久2年(1862)に息軒・宕陰と共に昌平坂学問所の儒官を拝命して「文久の三博士」と謳われます。維新後は新政府に出仕して昌平学校教授となり、退官後は再び漢学塾を開き、生涯で1400名もの弟子を育てました。
木下犀譚+
木下犀譚(韡村:1805-1867)は肥後国(熊本県)の豪農の生まれです。聡明だったことから、22歳の時に名字帯刀を許され、藩校「時習館」で学んだ後、江戸へ出て昌平坂学問所で佐藤一斎に師事し、後に松崎慊堂にも学びました。ここで安井息軒や塩谷宕陰と終生の親交を結びます。
木下犀譚は「文会」の立ち上げにも加わりました。『木下韡村日記』には「文会」の参加者やその回のテーマが、第1回から第24回まで記録されていて、その活動の様子が分かります。木野主計『木下韡村の生涯とその魅力』(p.122-p.134)に分かりやすく紹介されているので、ご参照ください。
犀譚は、中国の法律である明律や清律に通じていました。江戸時代の法律はもともと杜撰で、幕府や諸藩は明律・清律を参考にして法整備を進め、明治政府が明治3年に発布した刑法典『新律綱領』も明律と清律を参照にして作られたほどなので、犀譚の専門性は非常に希少でした。それで、息軒たちが昌平坂学問所の儒官を拝命した時、犀譚にも打診があったのですが、徳川直参になるために藩籍を棄ててねばならかったこともあり、犀譚は「自分を農民から取り立ててくれた肥後藩主に対して、まだ恩返しができていないので……」といって断ったそうです。
熊本へ戻った犀譚は藩校「時習館」で教鞭を取り、多くの逸材を育てました。弟子には横井小楠(1809-1869)や竹添井井(進次郎:1842-1917)、井上毅(1844-1895)がいます。
木下犀譚の墓碑銘は息軒が書きました。『北潜日抄』には、依頼していた木下犀譚の墓碑銘を受け取るという名目で、熊本から竹添進次郎(井井)が疎開先の領下村まで息軒を訪ねてきたと書いてあります。竹添は、後に安井息軒の『周礼補疏』の校訂を行い、その直筆原稿が慶応大学の斯道文庫に保管されています。
藤田東湖+
藤田東湖(1806-1855)は、水戸学者の藤田幽谷(1774-1826)の次男として水戸(茨城県)城下に生まれました。水戸藩主徳川斉昭の懐刀として藩政改革を推進しましたが、徳川斉昭が幕府から隠居蟄居処分を受けると、東湖も失脚して幽閉されます。幽閉生活は8年間に及びましたが、黒船来航をきっかけに徳川斉昭が海防参与として幕政に復帰すると、藤田東湖も江戸へ呼び戻され、幕府の海岸防禦御用掛となって徳川斉昭を支えます。
息軒が藤田東湖と初めて会ったのは、天保11年[1840]、松崎慊堂の家のことだとされています。若山甲蔵の「親善なる東湖」に詳しいのですが、初対面の印象は互いに最悪でしたがすぐに意気投合し、息軒は飫肥の弟子に宛てた書簡に「当時京阪の間、格別之人物も不承候。藤沢東涯と申者、人物は堅固之由承候、文も一二篇見候処、通例には出来申候。若儒家御交被成候はば、此人可然候」と書いています。
東湖は江戸へ戻ってきてからは、息軒たちの「文会」にも参加するようになりました。時節柄ずいぶんと踏み込んだ話もしていたようで、下田にロシア使節プチャーチンが来航した日に、藤田東湖から息軒に宛てて「話をしたいから拙宅に来て欲しい」という手紙を出していますが、最後は「世上はエビス講に候えども、僕は『攘夷会』をしたい微意に御座候う」という言葉で締められています。[「翁が安井息軒に与ふる書」]
息軒は水戸斉昭の諮問に答えて、斉昭より「足食足兵民信之」という掛け軸と家紋の入りの衣装を下賜されました[当館常設展示室]が、仲介の労をとったのは藤田東湖でした。しかし交際が再開して僅か2年後、藤田東湖は「安政の大地震」で自宅の下敷きになった母親を助けて圧死してしまいます。
藤田東湖が幽閉期間中に悲憤慷慨して作った『回天詩史』は、幕末の志士たちに愛唱されました。西郷隆盛もその一人で、島津斉彬に抜擢されて江戸へ出てきた時、真っ先に藤田東湖を訪ねています。そのころは息軒も藤田東湖と親しく交際していましたから、もしかしたら両者はどこかですれ違っていたりしたかもしれません。